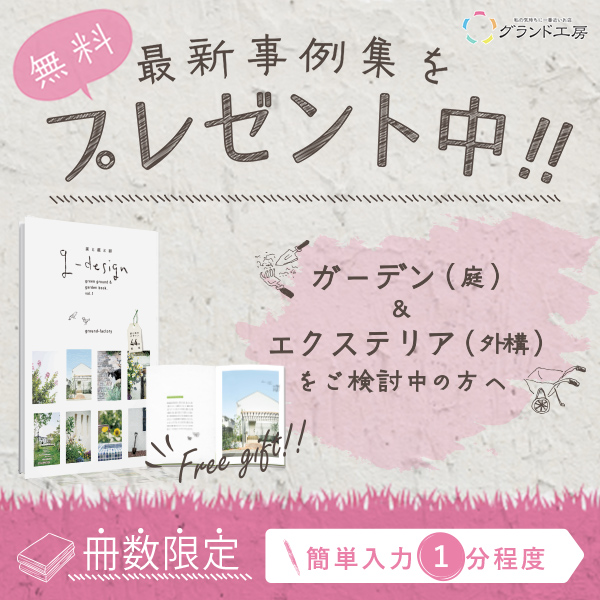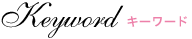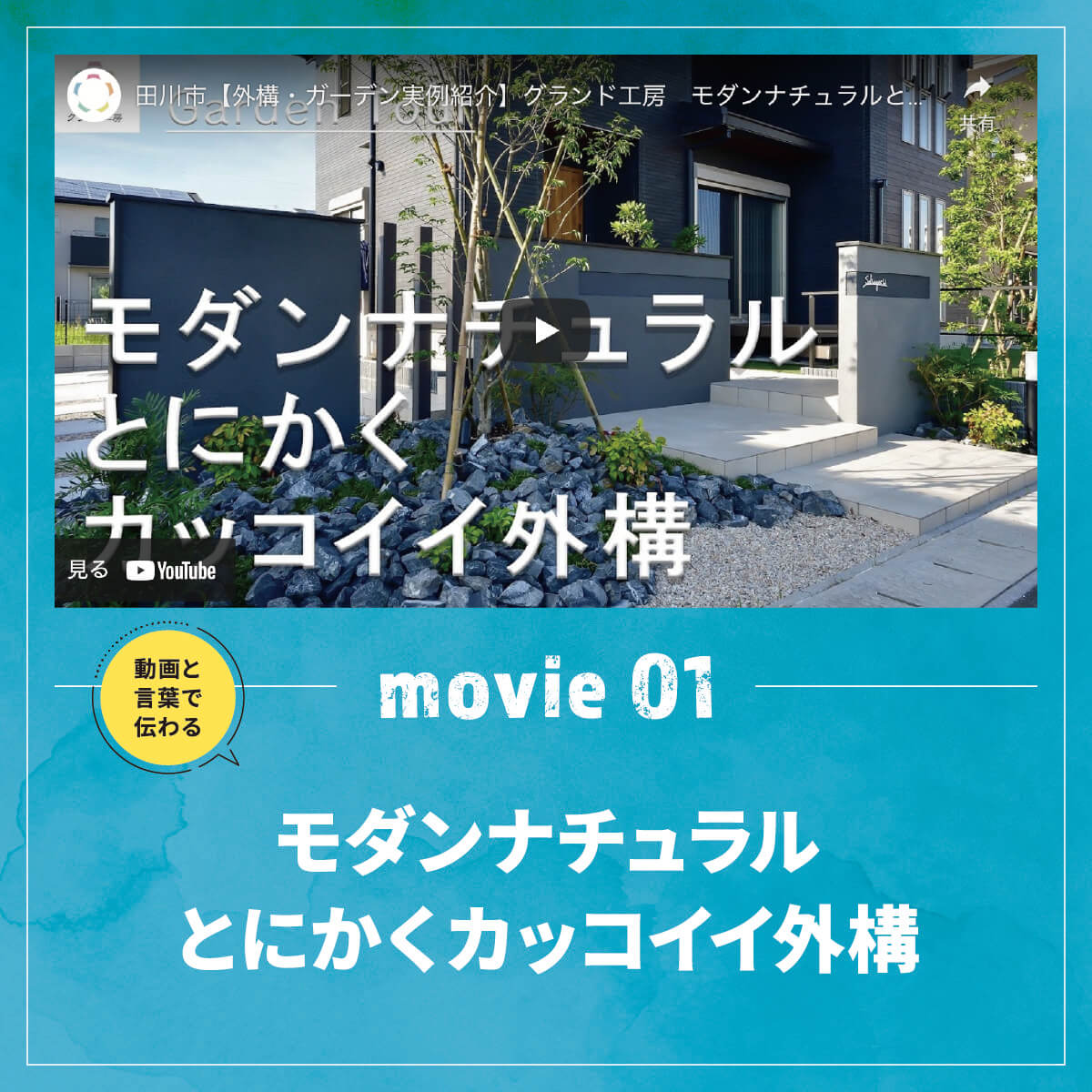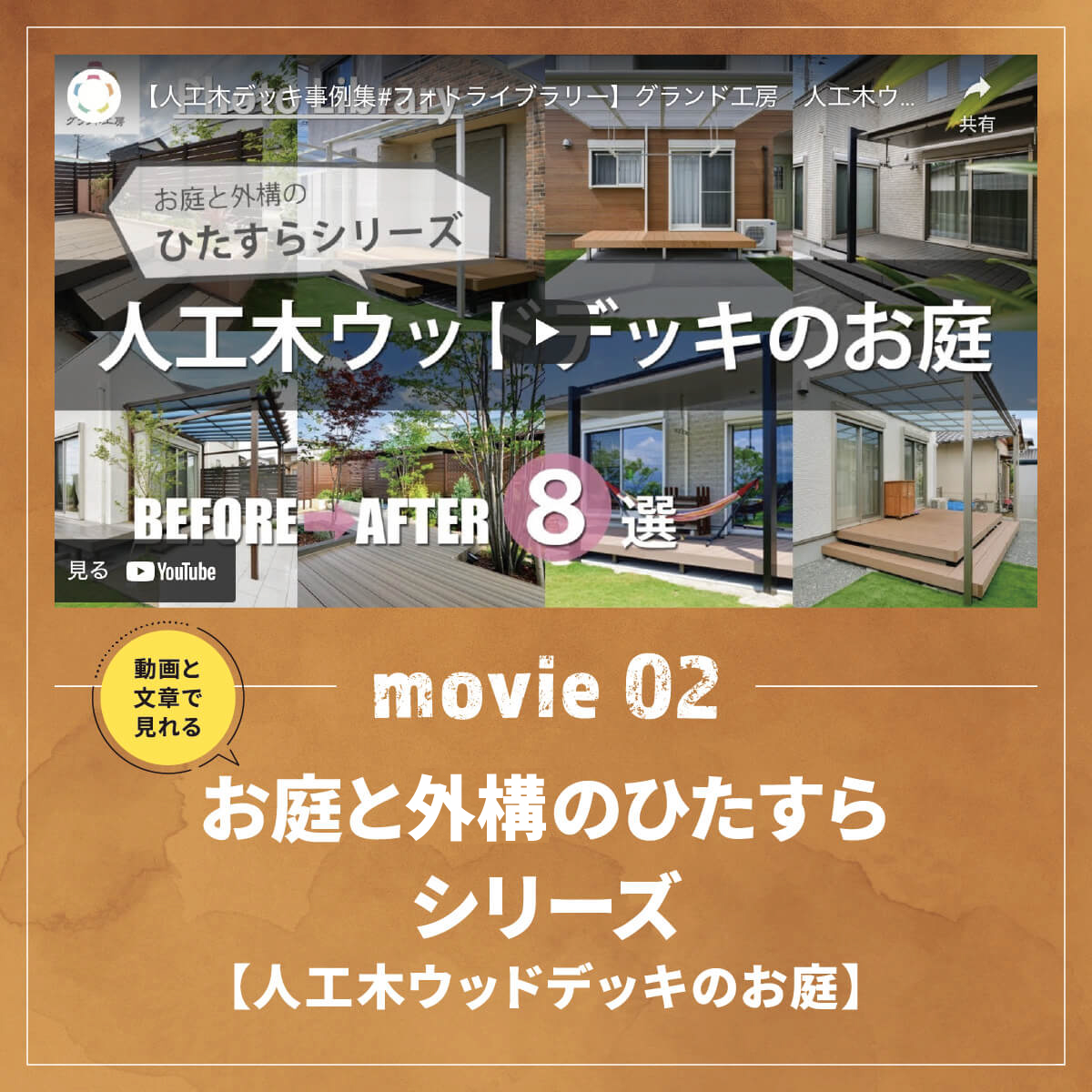2022/03/16 / 樹木・植物・メンテナンス
病気・害虫から大事な樹を守る 剪定の方法

暖かくなると一気に草木が芽吹き出して、新緑の気持ちのいい季節になります。
お庭に木を植えた後、「いつどんな風に剪定したらいいですか?」という質問も多く寄せられます。
切りすぎた場合以外は、剪定して枯れるということはほとんどありません。思い切って剪定するとお庭もスッキリします。
今回の記事では、主に春夏に向けた剪定の方法を中心にご紹介します。
今年はぜひ自分でチャレンジしてみましょう!
1.見た目を美しく整える
樹木は生き物です。放っておくと大きく成長して、見た目にもうっとおしくなってきます。
必要ない枝を落とすと、樹形を美しく整えることができます。
2.病害虫から樹木を守る
枝や葉が混み合ってくると、風通しが悪くなり、病気や虫を招く原因になります。
3.必要な枝に栄養が行き届くようにする
不要な枝があると、栄養が必要な場所に行き届かなくなってしまいます。
枝葉が広がり密集してきたら、年に2回、夏と冬に剪定するのが理想です。
花木は、花の終わる時期に剪定すると次の年の花付きがよくなります。花が咲く前に剪定する場合は、混み合った枝だけを切るようにして、なるべく花芽を残すようにしましょう。

剪定の作業をする時は、虫や枝から守るために、なるべく肌が露出しないようにします。
長袖・長ズボン、軍手を着用しましょう。
道具は基本的に以下の2点を用意します。
・剪定ばさみ
・手のこぎり

まずは幹ごと枯れている枝があれば切っていきます。
樹形にもよりますが、下の写真のように根元に緑がある場合は、そこから上を目安に切り落としましょう。

太い枝を切る時は、幹の両側面からのこぎりを入れるようにすると樹皮が剥けずにきれいに切ることができます。

桜など、木によっては切り口から雑菌や雨水などが侵入し、弱ってしまうこともあります。

その場合は、切り口に癒合剤(ゆごうざい)を塗っておきましょう。
ホームセンターや園芸用品店で扱っており、切り口を保護する役割を果たします。

次に、枯れている小枝を取り除いていきます.
枯れている枝はポキポキと簡単に折れるので、手で取り除くことができます。
反対に、生きている枝はしなるので、簡単に折れないのが見分けるポイント。
ハサミを使わずに枯れた小枝を取り除くだけでも、かなりスッキリとした印象になります。

ひこばえとは、樹木の切り株や根本から生えてくる若芽のことです。
放置していると樹形が乱れてしまったり、必要な栄養が木の先端まで行き届かなかったりします。

ひこばえは、思い切って根元から剪定はさみで切ってしまいましょう。
最初はどこから切っていいのか難しく感じてしまいますが、まずは枯れている枝を手で取り除くことから始めてみましょう。季節ごとに樹をよく観察しながらお手入れすることで、変化にも気づきやすくなりますし、愛着も湧いてきます。
ぜひやってみてくださいね!
関連記事の掲載
人気の記事
記事カテゴリー
記事キーワード
- グランドアートウォール
- SC
- 外構改修
- カーポートSC
- LIXIL
- LIXILショールーム
- テラスSC
- 展示物紹介
- LISILショールーム
- 展示場
- オーニング
- U.スタイル
- ベンチ
- タイル
- 新築外構
- シェード
- ガーデンリビング
- プラスG
- 家庭菜園
- 花壇
- 野菜
- リフォーム
- 紅葉
- 落ち葉
- お出掛け
- ファニチャー
- 家具
- ガレージ
- GAW
- 門まわり
- ビームス
- 折板屋根
- 三協アルミ
- 冬
- 手すり
- お金
- 予算
- 屋外コンセント
- 電気自動車
- EV充電
- テラスVS
- スタイルシェード
- インターロッキング
- ぐり石
- ご相談
- ディーズガーデン
- ウリンデッキ
- タイルテラス
- 物干しスペース
- テラス屋根
- 掃除
- 駐車場
- ベランダ
- 照明
- 日陰
- 水やり
- プール遊び
- 宅配ボックス
- 在宅ワーク
- 子ども
- 蚊
- おうち時間
- 手すり,ユニバーサルデザイン
- 物置
- ポスト
- 芝生
- ペット
- ガーデニング
- 外構
- お庭
- ガーデンルーム
- 雑草
- カーポート
- プライバシー対策
- デッキ
- フェンス
- 高齢者対応
- テラス
- 日よけ
- 害虫
- 自然石
- 節電対策
- 紫外線対策
- 人工芝
- レンガ
- 梅雨
- 玄関
- メンテナンス
- 防犯
- 水はけ対策
- 門塀
- 強風対策
- 雪対策
- 植栽
- 雑学
- 自転車
- 駐輪場
- 外壁
- 立水栓
- 表札
- インターホン
- 機能門柱
- 車止め
- お手入れ